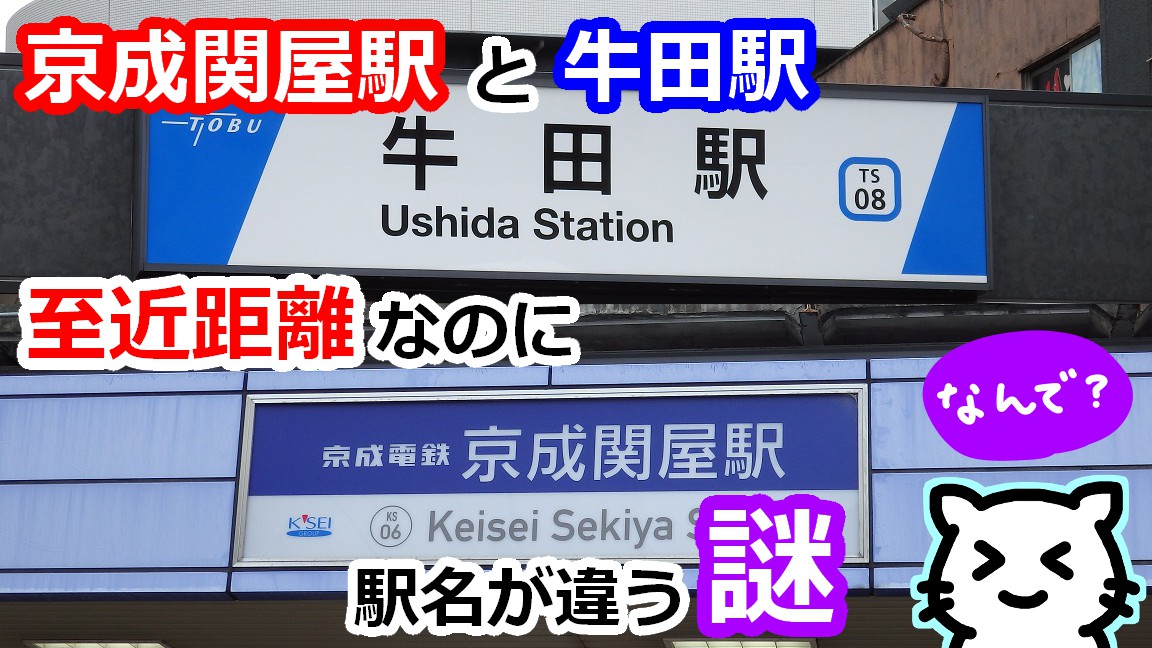鉄道車両ではほぼ当たり前ですが、車両側面に種別・行先の表示器を設置しています。ホームで待つ乗客に種別と行先を知らせるためです。
阪急においても例外ではありません。ただし、9000系・9300系まで、側面の種別・行先の表示器は独立して設置されていましたが、1000系から一体化した種別・行先表示器が採用されました。いったい何故なのでしょうか?
側面表示器の設置数
阪急では車両形式によって、1両当たりに設置されている側面表示器が異なります。
2022年3月時点における現役車両の側面表示器の設置数は、次の表の様になっています(8200系は特殊なので除外)。
| 形式 | 側面表示器の数 (1両片側) |
|---|---|
| 3300系 | 1個 |
| 5000系 | 1個 |
| 5100系 | 1個 |
| 5300系 | 1個 |
| 6000系 | 2個 |
| 6300系 | 2個 |
| 7000系 | 2個 |
| 7300系 | 2個 |
| 8000系 | 2個 |
| 8300系 | 2個 |
| 9000系 | 2個 |
| 9300系 | 2個 |
| 1000系 | 1個 |
| 1300系 | 1個 |
こちらは6300系の側面表示器。

種別と行先の側面表示器がかなり離れています。
こちらは7300系の側面表示器。

パワーウィンドウが設置されているので8300系と思えますが、7327F+7303Fです。
種別と行先の側面表示器が離れていますが、6300系ほどではありません。このスタイルは9000系・9300系まで引き継がれます。
2013年に登場した2代目1000系では、種別と行先が一体化された側面表示器が採用されました。

9000系・9300系までは側面表示器が種別と行先の2つでしたが、1000系で1つに減ったことになります。
側面表示器を1つに減らした理由は?
側面表示器を1つにした理由は、「阪急電鉄の都市交通事業本部 技術部 車両計画」の担当者が、『鉄道ファン』2014年2月号と『鉄道ピクトリアル』2014年3月で説明しています。
『鉄道ファン』2014年2月号 の「阪急電鉄1000・1300系」特集ページでは、「阪急電鉄の都市交通事業本部 技術部 車両計画」の担当者が、
車外表示器はフルカラーLEDとし,側面表示器は行先種別を一体表示とすることによって,視認性のさらなる向上を図っている.
―『鉄道ファン』2014年2月号 「阪急電鉄1000・1300系」
と説明があります。(『鉄道ピクトリアル』2014年3月号も同じ記述。)
つまり、「種別と行先が離れて表示されているよりも、くっついてた方が分かりやすいよね」という理由により、側面表示器が1つに減ったということになります。
実はコストカット?
ここで、幕式表示器とフルカラーLED表示器のメリットとデメリットを考えてみます。
| 幕式 | フルカラーLED | |
|---|---|---|
| メリット | 安い | 駅名変更の際に楽 |
| デメリット | 駅名変更の際に手間 | 高い |
導入コスト的には幕式表示器の方が有利ですが、例えば、終点駅に設定されている駅で駅名変更が発生した場合、幕の交換(発注および交換作業)に手間がかかります。
フルカラーLEDは駅名変更が発生した際にデータベースの値を書き換えるだけなので楽ですが、導入費と維持費は高いです。
こんなことは公には言えないと思いますが、高額なフルカラーLEDの側面表示器を2個から1個に減らすことで、コストカットを試みたと考えられます。5300系以前の形式でも種別と行先が一体化した側面表示器で問題無く運用出来ているので、種別と行先を一体化させても大丈夫と判断したのでしょう。
そもそも、行先・種別を分けていた意味は…?
2200系・6300系・6000系以降、側面表示器を2つにして、種別と行先を独立して表示させています。なのに、1000系では側面表示器が1つに減っています。
そうすると、2200系・6300系・6000系から9000系・9300系まで、「側面表示器を2つにしていた意味は何だったのか」と疑問が出てきます。
保守面で考えると、幕式の種別と行先の表示器が独立している方が、メリットがあります。
例えば、種別が5種類・行先が7駅ある場合で考えてみます(あくまでも例です)。
幕式表示器で種別と行先の表示器が一体化している場合は、5×7=35パターンの幕が必要です。一方、幕式表示器で種別と行先の表示器が独立している場合は、種別5パターン・行先7パターンです。
この状態で種別が1つ追加となると、6×7=42パターンの幕が必要となります。行先が1つ追加された場合でも、5×8=40パターンの幕が必要です。
上記のパターンはあくまでも例ですが、幕式表示器の場合、種別と行先が一体化していると、種別×行先のパターン分の幕が必要となり、種別や行先が増えると、物理的な上限に達してしまう可能性があります。それを未然に防ぐため、種別と行先を独立したと考えられます。
そして、2200系・6300系・6000系以前に製造された形式については、何故、改造工事の際に側面表示器を2個設置しなかったのかという疑問も残りますが…。
編集後記
種別と行先が独立してる側面表示器すき😽
参考文献
『鉄道ファン 2014年2月号』 交友社
『鉄道ピクトリアル No.887 2014年3月号』 株式会社電気車研究会
『阪急電車』山口益生著 JTBパブリッシング
『鉄道ピクトリアル No.837 2010年8月臨時増刊号 【特集】阪急電鉄』 株式会社電気車研究会
関連記事